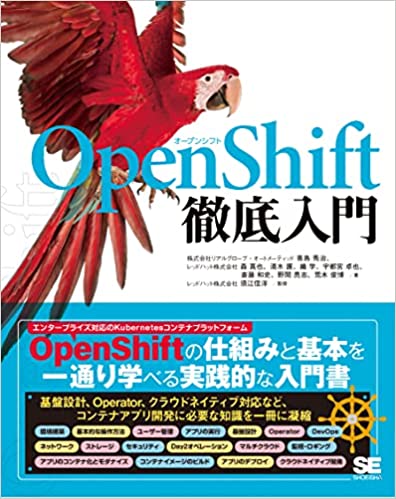2015年になってしまいました。
2014年に技術分野で印象に残ってること3つを思い返してみる。
1. インフラ会
@mogulla3と軽いノリで始めたインフラ会。
普段触らない、あるいは触ったとしてもすでに構築された環境で触ることの多いインフラ技術について
土日を使って自らの手で構築してみるといった会。
10月くらいから初めて以下を実際にやってみた。
- 仮想化 :Docker, Vagrant
- リバースプロキシ :Nginx
- ロードバランサー :HAProxy
- クラスタリング :Pacemaker+corosync(heartbeat)
- VPN :SoftEther
- 構成管理ツール :Ansible
- 自作PC
やったことについては全てではないがブログにまとめている。
- 【VPS1台でインフラ勉強】サーバ複数台構成、Nginxでリバースプロキシ構築 - Goldstine研究所
- 【VPS1台でインフラ勉強】HAProxyでロードバランサーを構築 - Goldstine研究所
- 【VPS1台でインフラ勉強】SoftEtherを使ってVPN構築 - Goldstine研究所
- 【年末遊び】秋葉原で自作PCパーツ集めて作った - Goldstine研究所
このインフラ会では3つを目標にしてたけど、これが仕事でも本当に役立った。
会もそうだが、目標にしていたマインドは今後もぜひ続けていきたい。
- "なんとなく知っている"をなくす
- 考える引き出しをふやす
- 自らの手で実践する
<大変参考になった書籍>
![[24時間365日] サーバ/インフラを支える技術 ?スケーラビリティ、ハイパフォーマンス、省力運用 (WEB+DB PRESS plusシリーズ) [24時間365日] サーバ/インフラを支える技術 ?スケーラビリティ、ハイパフォーマンス、省力運用 (WEB+DB PRESS plusシリーズ)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51uK4ACymiL._SL160_.jpg)
[24時間365日] サーバ/インフラを支える技術 ?スケーラビリティ、ハイパフォーマンス、省力運用 (WEB+DB PRESS plusシリーズ)
- 作者: 安井真伸,横川和哉,ひろせまさあき,伊藤直也,田中慎司,勝見祐己
- 出版社/メーカー: 技術評論社
- 発売日: 2008/08/07
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 133人 クリック: 2,270回
- この商品を含むブログ (289件) を見る
2. システム導入工事(工事監督マン)
仕事では主に社内SEなのだが、社内SEの仕事をしていると新規設備の導入工事なんかもまれにある。(IaaSとかつかってないので)
新規システムの導入で、データセンターへのサーバラックの立架工事など、インフラ機器の導入にいくつも立ち会った。
もちろんだが、私自身は工事をするわけではなく、あくまで立ち会い・監督の立場。
システム・ソフトウェア系の世界からは少し離れてるがインフラマンとしてはいい経験だった。
こんな仕事のおかげさまで、関西や北陸・四国など全国いろいろと行く機会があって、名物もかなり食べた笑
あとで、特に美味しかった名物料理を紹介するw
工事で一番大事なのはなんといっても「安全」。
安全第一である。
データセンターには無数のサーバやケーブルがある。もちろん自分が担当でないシステムの設備がたくさんある。
工事の際に過って、他の設備・機器・ケーブルを壊してしてしまった、切ってしまったなんていったらシャレにならない…
機器ならまだよいが、人的被害を出してしまったら…
そのためにも以下をきちんとしておくことが最重要。
- 事前の現地調査
- 工事場所はどこか?
- 対象機器はどれか?場所はどこか?(ケーブルなどの接続先)
- 十分な場所はあるか?
- 段差などの危険ポイントはどこか?
- 荷物はどうやって運ぶか?
- 工事内容の手順書・確認項目
- 上でよく確認したポイントが踏まえてあるか?
- 実施する内容は明確か?
- 監督側としてなにをどう確認すればいいか明確か?
- 現地の人とのネゴり
- あとはいろいろと聞けるようにデータセンター管理者と仲良くしておきましょう笑
ラックの立架といっても、電気もひかなければいけないので、電気工事もある。
あまりにも電気的知識がなさすぎて電気の入門の本も買ってしまった…

- 作者: 松原洋平
- 出版社/メーカー: オーム社
- 発売日: 2001/03
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
3. ブラックボックスをなくした開発組織を作る
好きなようにやりたいようにシステムやスクリプトを勝手につくってブラックボックスができる…
そしてそんなブラックボックスが運用される…
こんな状況はきっとどこにいってもあるものだと思う。
でも、なんとかこのブラックボックスと化する状況をなくそうと以下の様な取り組みを行ってきた。
(1) 使用する技術のある程度の統一化
業務の特性上、ひとつのシステムを作るというよりは、業務系システムを数十とあるのだけど、
個人の好き勝手に作ると言語も乱立し保守不可・改修難となるので、ある程度技術を統一化していくことに取り組んだ。
そうすることで、ブラックボックスの排除はもちろん、チームとしての技術の習得スピードも上がっていった。
(2) Gitlabを使った開発フローの確立
恥ずかしながら、すべてのシステムできちんとバージョン管理ができている状況ではなかった。
Gitlabを使った開発フローをルール化し、文化的に浸透させる取り組みを行っていった。
Merge Request(Pull Request)のおかげで好き放題に作られたソースコードが減った気がする。
(3) Ansibleでインフラも明確化
上2つで、アプリケーションレベルでのブラックボックスはある程度解消できてきたが、
インフラレベルでは依然としてブラックボックスのままだった。
こちらについてはAnsibleの導入と文化的に浸透を行っていった。
<大変参考になった書籍>

チーム開発実践入門 ~共同作業を円滑に行うツール・メソッド (WEB+DB PRESS plus)
- 作者: 池田尚史,藤倉和明,井上史彰
- 出版社/メーカー: 技術評論社
- 発売日: 2014/04/16
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (8件) を見る
4. まとめ
今年だけに限ったことではないけど、
ネットワーク系、インフラを支えるミドルウェア系、システムの開発系、システム導入工事系と
本当に多岐にわたる分野に携わり、システムを全体的に俯瞰して見れるようになってきたなーという実感がでてきた。
2014年は特にテクノロジーという側面で強くそれを感じた年だったと思う。
これからどういう分野で生きていくか、それはとりあえずは流れに身を任せてドリフトするとしよう。
エンジニアも知っておきたいキャリア理論入門(11):金井壽宏教授が提唱する「節目」のキャリア論 (1/2) - @IT
5. 【おまけ】各地のうまかったもの
大阪 お好み焼き
大阪 おでん
金沢 海鮮丼
香川 うどん
広島 あなご
広島 お好み焼き